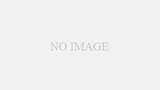バス釣りの世界でビッグバスを仕留めるためには、ただ目立つだけでなく、バスに違和感を与えず自然に口を使わせる演出力が求められます。その両立を高い次元で実現したルアーが、クラップバザーです。6インチという迫力のあるサイズに加え、絶妙な質感と設計により、警戒心の強いビッグバスの本能を直撃します。静と動の緩急を自在に操れるその性能は、まさに“ギャップで喰わせる”というコンセプトの体現と言えるでしょう。
クラップバザーの特徴
クラップバザー最大の特長は、動かない「静」のボディと、微細に水を掻く「動」のテールが生み出すメリハリのあるアクションです。特に注目すべきはそのテール設計。あえて自発的に動かないよう設計されたテールは、スイムスピードの変化に応じて「急に動き出す」「パタッと止まる」といった極端な変化を見せます。このギャップこそが、警戒心の強いバスに対してリアクションバイトを誘発する大きな要因となっています。
ボディは扁平形状で、ロールやウォブルを抑えて直進的に泳ぐことで、バスに警戒心を抱かせないI字系アクションを実現。そのうえで、テールだけがピリピリと繊細に動くことで、まるで小魚が水を掻くようなリアルな演出が可能になります。素材はソルト配合を抑えた浮力重視の設計で、モチモチとした質感が水をしっかり受け止め、ナチュラルな波動を生み出します。側面のみにリブを配置することで、実際の小魚と同様に横方向への波動が強調され、よりリアルな存在感を発揮します。
また、背面と腹面にはフックセッティング用のスリットを配置し、誰でも簡単かつ正確にフックセットが可能。背面スリットにはフックポイントを隠すためのリブも備えられており、ウィードレス性とフッキングのバランスも秀逸です。さらに、シュリンプ、イカ、ベイトフィッシュの成分をミックスしたスペシャルフォーミュラを配合することで、嗅覚による喰わせ要素もプラスされています。
クラップバザーの使い方
クラップバザーの基本的な使い方としてまず挙げられるのが、ノーシンカーやネイルリグによるスイミングです。直線的なボディの動きとテールのピリピリアクションのコントラストで、スレたバスの視覚と聴覚を刺激します。ゆっくりとただ巻きするだけで無警戒に泳ぐ小魚を演出でき、プリスポーン期の中層に浮いたメスバスなどに特に効果的です。さらに、巻くのを止めることでテールがピタリと止まり、水平姿勢でスローフォール。これが喰わせの間を生み出します。
リトリーブジャークでは、一定スピードで巻いて止め、素早く2〜3回巻き直すことで、テールの動きに急激な変化を加え、反射的なバイトを狙えます。また、ボトムまで沈めてショートジャーク&ポーズを繰り返す「ボトムジャーク」では、エビの跳ねるような動きを演出可能。高比重ボディによる素早いアクションと、スローフォール中のピリピリテールで、低活性バスにも強くアピールできます。
リーダーレスダウンショットやテキサスリグでの使用も効果的です。ただ巻きやズル引きでレンジコントロールをしやすく、シンカーの重さで速度や泳層を自在に調整できます。特に、シンカーが障害物に当たったタイミングでのストップでは、テールの急停止が喰わせの引き金になります。リフト&フォールでは、フォール中に止まるテールと、リフト時に突然動き出すテールの対比でリアクションを狙います。カバー際では「ハングオン・ハングオフ」で、引っ掛けて止め、外して動かすというテクニックが有効です。
フックは6/0以上のワイドギャップオフセットを推奨し、テールの先端が下を向くようにセットすることで、最も自然なアクションが得られます。琵琶湖の実釣では、数々の50アップを叩き出し、特に大型バスへの威力が証明されています。
クラップバザーは、喰わせとリアクション、ナチュラルとアピール、その相反する要素を見事に融合させたビッグバス特化型ルアーです。どんな状況でも信頼して投入できる、アングラーにとって心強い選択肢となるでしょう。
クラップバザーのインプレ
エバーグリーンのクラップバザーのインプレを紹介します。
#バス釣り #bassfishing #エバーグリーン
デスレイクで有名な緑川ダムに行ってきました🙄(曇り時々小雨)
ボーズ覚悟でクラップバザー投げたら、緑川ダムのバス反応するする!!😳
2回フッキングミス💦3回目で釣ることが出来ました😆
1匹だけど、とても価値ある1匹👍
緑川ダム攻略見えてきたかも💪 pic.twitter.com/5CAKKJZD5W— Masato Kanezaki (@KanezakiMasato) June 13, 2023
今年初バス釣ってきた。買ってよかったクラップバザーとジャックハンマー pic.twitter.com/fEPMm8oF6W
— ヌシ (@nushi_sknokf) April 27, 2023